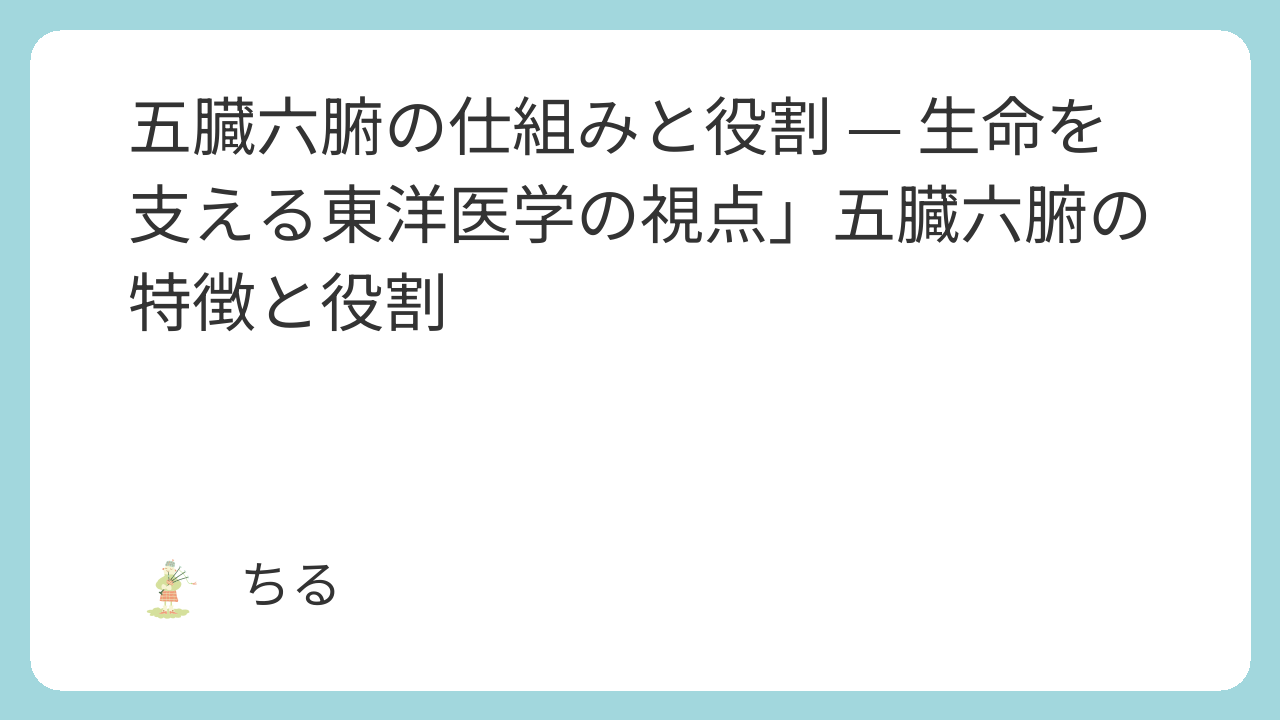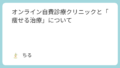五臓六腑の特徴と役割
五臓六腑という言葉を聞いたことがあるでしょうか。
中医学つまり漢方で使われる言葉で、5つの臓と6つの腑が生命を維持していてそれぞれに役割があると考えられます。
中医学の臓なので、西洋医学の臓器と少しちがっていて、大事な臓器を思い浮かべた時
心臓、肺臓、腎臓、肝臓はわかりますが、あれもうひとつは?と思うかもしれません。
もう一つは脾臓です。中医学的には脾臓は、消化に関連する臓とされています。
🔹 五臓(精気を「蔵する」臓)
五臓は、体の基盤となる気・血・津液・精を蓄え、全身を養う働きを持ちます。
精神や情緒とも深く関わり、「中枢システム」に近いイメージです。
- 肝(かん)
- 特徴:気血の流れをスムーズにする「疏泄作用」。血を貯える「蔵血作用」。
- 役割:気血を調整し、筋や目、情緒の安定を保つ。ストレスや怒りで肝の働きが乱れる。
- 心(しん)
- 特徴:血を全身に巡らせ、精神活動(神志)をつかさどる。
- 役割:循環器と精神の中枢。喜びすぎると心を傷めるとされる。
- 脾(ひ)
- 特徴:飲食物から気血を生み出し、全身に供給する「後天の本」。
- 役割:消化・吸収・代謝の中枢。思い悩みすぎると脾の働きが低下。
- 肺(はい)
- 特徴:呼吸によって「清気」を取り入れ、全身に気を配る。
- 役割:免疫や水分代謝を調整。憂いや悲しみで機能が弱まる。
- 腎(じん)
- 特徴:生まれ持った「先天の精」を蔵し、成長・発育・生殖を支える。
- 役割:ホルモン系・腎泌尿・骨や耳の働きと関連。恐れが腎を傷める。
🔹 六腑(飲食物を「受け入れ・伝化する」腑)
六腑は基本的に「空」であり、外界から入る飲食物や水分を処理・運搬し、排泄へ導きます。
生命維持に直結する「消化・吸収・排泄システム」といえます。
- 胆(たん)
- 特徴:胆汁を貯え出し、消化を助ける。
- 役割:決断力や勇気を支えるとされる。
- 小腸(しょうちょう)
- 特徴:飲食物を「清(栄養)」と「濁(不要物)」に分ける。
- 役割:栄養を吸収し、不純物を大腸や膀胱へ送る。
- 胃(い)
- 特徴:「受納」と「腐熟」の機能=飲食物を受け入れ、消化する。
- 役割:栄養を取り込む入り口で「水穀の海」と呼ばれる。
- 大腸(だいちょう)
- 特徴:不要物を体外に排泄。
- 役割:便通を司り、腸内環境とも関係。
- 膀胱(ぼうこう)
- 特徴:尿を一時的に貯めて排泄する。
- 役割:腎や三焦と連携して水分代謝を維持。
- 三焦(さんしょう)
- 特徴:形のない腑。上焦(胸)、中焦(腹)、下焦(骨盤)に分かれる。
- 役割:気血水の通り道を調整する「水道の通路」として働く。
🔹 全体としての特徴と生命維持の意味
- 五臓は「エネルギーや精神活動の貯蔵庫」
→ 気血津液・精をつくり出し、精神を安定させる。 - 六腑は「取り入れ・変化・排泄の通路」
→ 食べ物を受け入れ、栄養に変え、不要物を排泄する。 - 両者が互いに補い合うことで、
- 飲食物 → 気血津液に変換
- 呼吸や循環 → 生命エネルギーの供給
- 精神活動の安定 → 生きる力を保つ
つまり、五臓六腑は「体を養い、動かし、保つ」二つのシステムが噛み合った全体モデルといえます。
五臓六腑が弱ってきた時、生命システムは弱まり、さらに弱まると終わりを迎えると考えた時、
脳や神経が入っていない理由がわかります。認知症や足の痛み、脊柱管狭窄症などでは生命は終わりを迎えることができないです。脳梗塞もほかの臓器まで影響がなければ生きながらえることができます。
五臓六腑は互いに影響しあっていて、一つが弱ると徐々にほかの臓腑にも影響が回り最後は、生命システムが終わりを迎えるというよくできたシステムだと改めて感じました。